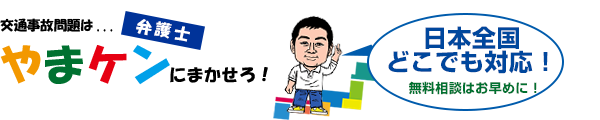入通院慰謝料の考え方と計算方法について

交通事故の被害に遭われたことがなくても、「慰謝料」という言葉をご存知の方は、比較的多いのではないでしょうか。
慰謝料の正確な意味は、「被害者が負った精神的損害(ショックやストレスなど)に対する損害賠償金」です。
慰謝料にもいろいろとありますが、交通事故(死亡事故を除きます)の慰謝料は、「傷害に対する慰謝料」と「後遺障害に対する慰謝料」とに分けて考えられます。
そのうち「傷害に対する慰謝料」は、「傷害慰謝料」や「入通院慰謝料」と呼ばれています。この記事では、入通院慰謝料の考え方や計算方法、計算の基礎となる入通院期間などについて説明いたします。
目次
入通院慰謝料を計算する基準
入通院慰謝料の金額は、交通事故により負ったケガの状況によって変動しますが、ある程度の目安となる慰謝料を算出する基準はあります。
個々の交通事故においては、その基準から算出される「目安の慰謝料」に増減の調整を加えることで、実際の慰謝料の金額が決められるのです。これは裁判であっても交渉による示談であっても同じことです。
3つの基準
慰謝料を算出する基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、そして裁判基準の3つがあります。
まず、自賠責保険基準とは、自賠責保険会社から支払われる保険金額を定める基準です。最低限の補償を目的としているため、基準額は低く、また限度額も低めに設定されています。
次に、任意保険基準とは、それぞれの任意保険会社が規定に基づいて支払う保険金額を定めた基準で、当然ながら保険会社によってその基準は異なります。
任意保険基準は保険会社ごとに異なりますが、ほとんどの場合は自賠責保険と弁護士基準の間の金額を算出することになります。
最後の裁判基準とは、仮に裁判になったとした場合に、被害者が受け取れる可能性の高い金額を定めた基準です。
この3つの基準で算出される保険金額はそれぞれ異なります。裁判基準が最も高額な慰謝料を算出し、その額は、自賠責保険基準の倍近くになることもあります。
入通院慰謝料の入通院期間
このように、入通院慰謝料を計算する際には3つの基準がありますが、これらの基準は、入通院期間が長ければ長いほど高額な慰謝料が算出されるという点では共通しています。
では、入通院期間は具体的にどのように決まるのでしょうか。基準ごとに入通院期間の決め方をみてきましょう。
自賠責保険基準による入通院期間
国土交通省発表の「自賠責保険の保険金等及び自賠責共済の共済金等の支払基準」(平成13年)によると、自賠責保険の慰謝料の対象日数は「被害者の傷害の状態、実治療日数などを勘案して治療期間内で決められ」ます。
具体的な運用においては、「通院期間」か「実通院日数の2倍」のうちの少ないほうが「対象日数」になります。
裁判基準による入通院期間
裁判基準では、入通院期間は入院期間と通院期間とに分けて考えます。
- 入院期間とは、実際に入院していた期間のことを指します。
- 通院期間とは、これも原則として実際に通院していた期間のことを指します。
ただし、以下の2通りの例外があります。
- 例外1:通院が長期にわたる場合には、症状や治療内容、通院の頻度などを考慮して、実通院日数(実際に病院に通った日数)の3.5倍の日数を通院期間とすることがあります。
- 例外2:むち打ち症で他覚症状(医師などの第三者が客観的に認識できる症状)がなく、かつ通院が長期にわたる場合には、症状や治療内容、通院の頻度などを考慮して、実通院日数の3倍の日数を通院期間とすることがあります。
任意保険基準による入通院期間
任意保険については、各保険会社がそれぞれ慰謝料の計算方法を定めています。また、それらは公開されていません。
そのため、入通院期間の算出方法についてもハッキリしたことは言えません。
ただ、結果として算出される慰謝料の金額は、裁判基準に比べてかなり低いということは覚えておきましょう。
入通院慰謝料の計算式
入通院期間の決め方を理解したところで、入通院慰謝料を実際に計算する計算式も確認しておきましょう。
自賠責保険基準による計算式
自賠責保険の入通院慰謝料の金額は、以下のように計算されます。
- (1日あたり4,200円)×(上述の「対象日数」)
裁判基準による計算式
裁判基準で算出される慰謝料額は、日弁連交通事故センター東京支部が発行している交通事故に関する専門書「赤い本」に掲載された表を見ることで知ることができます。
- 入院したが退院後は通院しなかった場合:「入院期間」のみを使います。
- 入院せずに通院だけした場合:「通院期間」のみを使います。
- 入院後に通院もした場合:「入院期間」と「通院期間」を両方使います。
最大限の慰謝料を獲得するためには弁護士に依頼
弁護士が交通事故被害者より依頼を受け、代理人として交渉にあたる際には、上記に説明した3つの基準のうち、最も多額の慰謝料をもらえる可能性の高い「裁判基準」を用いて算出した金額を主張することになります。
しかし、裁判基準はあくまで裁判をしたときの基準ですから、裁判基準の金額どおりに示談できることはほとんどありません。どうしても裁判基準の金額を得ようとするなら裁判によるしかないでしょう。
また、弁護士を代理人に立てることにより、相手方にプレッシャーを与え、できる限り裁判基準に近い金額を狙うという方法もあります。
また、示談がまとまらない場合は民事訴訟になりますが、その場合はほとんどの場合、相手方も弁護士を代理人に立ててきます。そのため、訴訟になったら必ず弁護士を立て、不利にならないようしっかり準備をしてください。